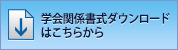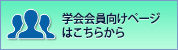�V�����E���̗\��
|
| ��143���� | ���� | 2026�N10�����{�`���{�i����j |
|---|---|---|
| ��� | ���u�Б�w���o��L�����p�X | |
| ���e | �ڂ�����143�����̍����������������B |
- �T ����̃J�e�S���[ �i��̗�F�J���_��@20���i���V�^�A�����j�Ȃǁj
- �U �@�����̃J�e�S���[ �i��̗�F����J����������Ȃǁj
- �V ��b���_�̃J�e�S���[ �i��̗�F�i�����I�ȁj�J���@�̗v�ہE���݈Ӌ`�Ȃǁj
- �W ������̉ۑ�̃J�e�S���[�i��̗�F�p���[�E�n���X�����g�Ȃǁj
- �X ��r�J���@�E���ۘJ���@�̃J�e�S���[
- �Y ���̑��̃J�e�S���[�i��̗�F�Ȍ���e�[�}�A�u�b�N�E���r���[�Ȃ�
��\��������̃��b�Z�[�W
��\�������b�Z�[�W
���{�J���@�w��́A�J���@�̌����y�щ���̑����͂̑��i����ړI�Ƃ��āA1950�N10���ɑn�݂���A���݂܂�75�N�ɋy�ԗ��j��ςݏd�˂Ă��܂����B�e���ōs�����c�_�̓��e�́u���{�J���@�w��v�Ɍf�ڂ���A�������ʂ��Љ�ɔ��M���������S���Ă��܂��B�܂��A�{�w��́A����̐ߖڂ��ƂɁA�J���@�w�̗��_�I���B�_�𖾂炩�ɂ��ׂ��A�w�J���@�u���x�i�S7���E1956-59�N�j�A�w�V�J���@�u���x�i�S8���E1966-67�N�j�A�w����J���@�u���x�i�S15���E1980-85�N�j�A�w�u�� 21���I�̘J���@�x�i�S8���E2000�N�j�A�w�u���J���@�̍Đ��x�i�S6���E2017�N�j��ҏW�E���s���Ă��܂����B
���w��̌����Ώۂł���J���@�̕���ɂ����ẮA�Љ�o�Ϗ̕ω��ɔ����A�@�I�Ή������߂���l�X�Ȗ�肪���N���Ă��܂����B���Ă͊����̖@���x��O��ɖ@���߂ɂ��c�_�����S�ł������A1980�N�㔼����͎Љ�o�ύ\���̕ω���ٗb�W��̐V���ȉ��l�̑䓪�ɑΉ������V���@�E�@�������������A���@����̏d�v�������債�Ă��܂����B�����I�ɓ����Ă�����J���s��̍\���ω��A���Z�p�̍��x���A��������J���҂̑��l���A��ƍ\���E�s���̕ω��A�z��O�̎��ԂƂ������Ȃ��Ȃ������R�ЊQ��p���f�~�b�N���A�ٗp�V�X�e���͑傫�ȕω��ɒ��ʂ��Ă���A�J���@�w�ɂ́A�V���ȘJ�������̉ۑ肪���X�ƒ�N����Ă��܂��B����݂̂Ȃ炸�A�J���@������܂ŏ��^�̂��̂Ƃ��Ă����J���ҁA�g�p�ҁA���ƁA�W�c�I�J�g�W�Ȃǂ̊�b�I�T�O�����Č����A�V���ȘJ���@�݂̍�悤���������ׂ�����ɓ����Ă���̂�������܂���B
���������J���@�̉ۑ�ɓK�Ɍ����������߂ɂ́A���̖@����A���̌����̈�Ɋw�тA�J���@�̑��݈Ӌ`�A���̉ʂ����ׂ��������Ċm�F���邱�Ƃ��K�v�ł��傤���A���̂��߂ɂ���b���_�����E���j�����E��r�@�����܂����l�@���v�������ł��傤�B�����̊w�p�����́A�����҂��P�Ƃɍl�����邱�Ƃɂ���ĂȂ����邱�Ƃɂ͌��E������A�����ғ��m���l�X�Ȏ��_��v����w�i�ɁA���R舒B�ɋc�_�����킷���Ƃɂ���Ă����A�����̐i�W��[�����}�邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�J���@�w��́A�܂��ɂ��̂悤�ȘJ���@�������u���҂̌𗬂̏�A���������̏�������̂ł��B
���w��ɂ������Ȍ������\��c�_�̏�Ƃ��ẮA�N1��̑��ɂ������V���|�W�E���A���[�N�V���b�v�A�ʕ�����Ȃ��̂ł��B�҃O���[�v�ɂ�鑽�p�I���{�i�I�Ȍ������Ȃ�����V���|�W�E���A��b���_�I�ȃe�[�}��������Ɨ��_�̉ˋ��ƂȂ�e�[�}�܂ŁA�ҁE�t���A���݊Ԃ̎��R舒B�ȋc�_�����҂���郏�[�N�V���b�v�A�V�i�C�s�̌����҂𒆐S�ɌX�̌������ʂ𐢂ɖ₤�ʕȂǁA����̖��S�ɉ��������j���[���p�ӂ���Ă��܂��B�����ɎQ�����邱�ƂŁA��������݂ɒm�I�h�����A�V���Ȓ��z�Ă��ꂼ��̌�����i�������A���邢�͋��������̌_�@�W�����邱�ƂȂǂ�ʂ��āA�J���@�����̐�������w���܂��Ă������Ƃ����҂���܂��B
������A�J���@�w��w����ɂƂ��Ă��Љ�ɂƂ��Ă��L�Ӌ`�ȑ��݂ł��葱����悤�ɁA�w�͂��d�˂ĎQ�肽���Ǝv���܂��B
���{�J���@�w��Ƃ�
�ݗ�
���{���@�w��́A1950�N�i���a25�N�j10��27���ɐݗ�����܂����B�n������́A��130���̎Q���҂������đ�㏤�H��c���ŊJ�Â���܂����B�ړI
�u�J���@�̌�����ړI�Ƃ��A���킹�Č����ґ��݂̋��͂𑣐i���A���O�̊w��Ƃ̘A���y�ы��͂�}�邱�Ɓv�i�K���3���j�ł��B�w��̂��ē� >> �w��K��
����̍\��
�{��ɂ́A�����ҁA�ٌ�m�Ȃǂ̎����Ƃ���ъ�ƂȂǂ̐l���J���S���҂̕��Ȃǂ𒆐S�ɖ�700���̕����Q�����Ă��܂��B��Ȋ���
�N1��̑��Ɗw��̔��s����Ȋ����Ƃ��Ă��܂��B�w����͏H�i10���j�ɊJ�Â���A�V���|�W�E���A�ʕA���[�N�V���b�v�Ȃǂ��s���܂��B
���{�J���@�w��́A���̑��ł̕��e�𒆐S�ɍ\������Ă��܂��B
���̂��ē� >> ���̗\��
���{�J���@�w�����
�w��̘A����
��102-8160 �����s���c��x�m��2-17-1�@����w�@�w�� ���c��V������
e-mail�Frougaku@gmail.com
�⍇�킹�t�H�[��
�����肢
�{��ɂ��A���̍ۂɂ́A�Ȃ�ׂ��A�⍇�킹�t�H�[���Ee-mail�������p���������B
�����NjƖ��ȗ͉��̂��߁A�d�b�y��FAX�ɂ�邨�⍇�킹�͂��ł��܂���B
���������������B